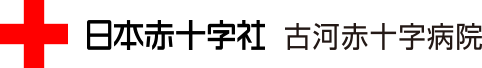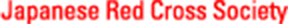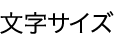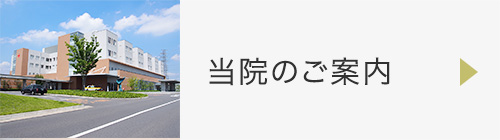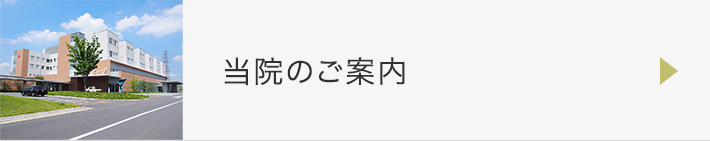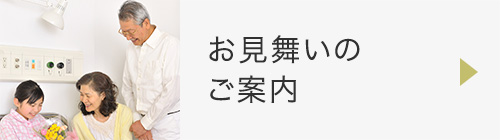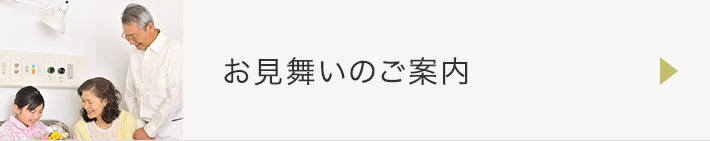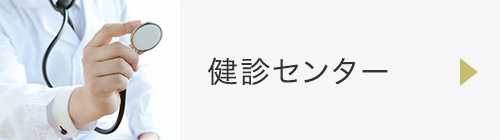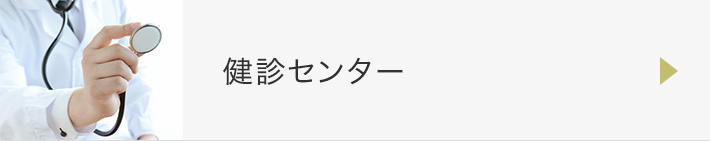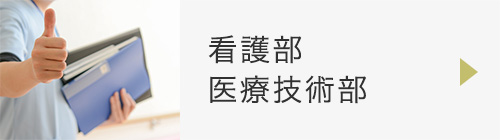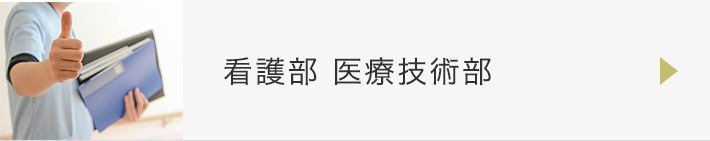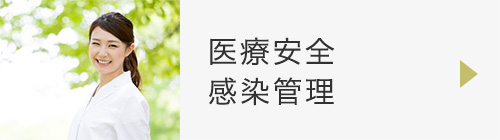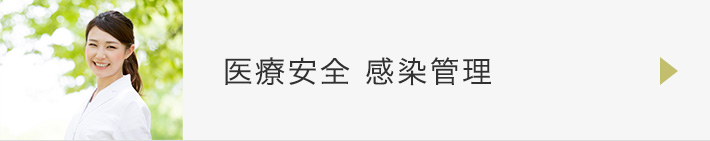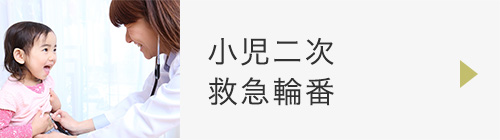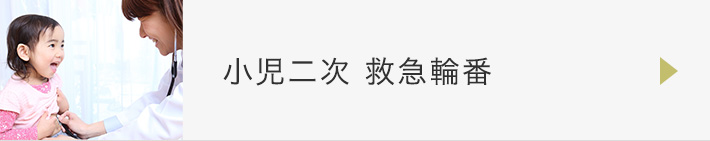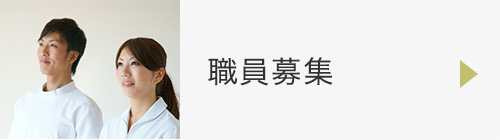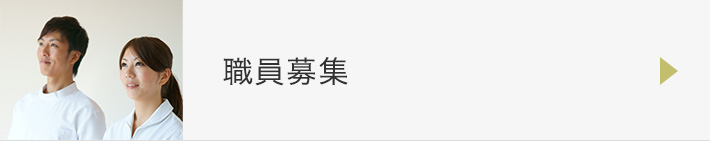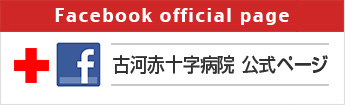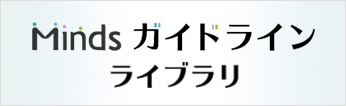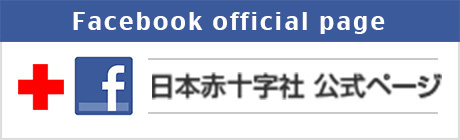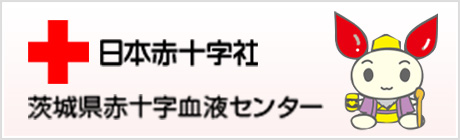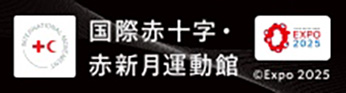各診療科のご案内
腎・高血圧科
診療担当
| \ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 第1・3 |
| 午前 | 渡邊(祐) |
- | - | 本間 |
野中 |
- |
| 午後 | - | - | - | 安藤(第3) |
- | - |
担当医
ノナカ ヒロアキ
野中 宏晃
(常勤)
腎臓内科
琉球大学出身
内科専門医
※令和7年6月2日付着任予定
ワタナベ ユウサク
渡邊 祐作
腎臓内科
ホンマ スミコ
本間 寿美子
(非常勤)
アンドウ ヤスヒロ
安藤 康宏
(非常勤)
腎・高血圧科(日本腎臓学会研修施設、日本透析医学会教育関連施設)
慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症やループス腎炎などの続発性腎疾患、急性・慢性腎不全など腎疾患を多岐にわたって診療しております。また、以下のように初期段階から末期腎不全・透析に至るまで腎疾患全般を総合的に診断・治療しています。
腎臓疾患ではその経過中に高血圧を伴いやすく、その血圧の管理は腎臓の予後と密接な関係があり、また逆に長い期間高血圧が持続すると腎機能障害(腎硬化症)をきたすことから、"腎臓"と"高血圧"には強い関連があるため、高血圧も併せて診療しています。
診療内容(腎臓内科)
(1)慢性糸球体腎炎の初期段階やネフローゼ症候群などに対し積極的に腎生検を行い、診断を確定するとともに腎生検結果に基づいた早期治療を行っています。なかでもIgA腎症は慢性糸球体腎炎の中で最も頻度が高い病型であり、近年、発症後 20年で20~40%が末期腎不全に陥ることが分かっています。そのため、IgA腎症の根治・寛解を目指して、口蓋扁桃摘出術+ステロイドパルス療法が日本では広く行われており、良好な結果が得られています。当院でもIgA腎症に対して積極的に口蓋扁桃摘出術+ステロイドパルス療法を行っています。
(2)慢性腎不全に移行した症例では食事療法を中心とし薬物療法を併用しながら末期腎不全への進行をできるだけ緩徐にすることを目標としています。
また、食事療法などの治療を含め、腎不全についてより理解して頂くための短期入院も行っています(約8日間)。
診療内容(高血圧内科)
高血圧内科では高血圧の正しい診断と評価、治療方針の決定などエビデンスに基づく診療を行います。
(1)二次性高血圧の頻度は約10%程度といわれています。その中で腎疾患に関連した腎実質性高血圧が最も頻度が高く(高血圧全体の2~5%)、最近では原発性アルドステロン症が従来考えられていたより多い(高血圧全体の3~10%)と考えられています。
二次性高血圧(原発性アルドステロン症を含む副腎腫瘍による内分泌性高血圧や腎動脈の狭窄が原因で生じる腎血管性高血圧など)は、腫瘍の摘出などで治る高血圧であり、それらの二次性高血圧を正しく診断します。
(2)家庭蓄尿で評価した食塩摂取量に基づいて減塩指導を行うなど、高血圧ガイドライン2009に準じた生活習慣の修正による高血圧の治療を推進します。
表2.生活習慣の修正項目
| 1.減塩 | 6g/日未満 |
| 2.食塩以外の栄養素 | 野菜・果物の積極的摂取(重篤な腎障害、肥満や糖尿病では勧められてない) |
| 3.減量 | BMI (体重(kg)÷身長(m) ÷身長(m)=25未満目標体重=標準体重(身長(m)X身長(m)X22) |
| 4.運動 | 中等度の強度の有酸素運動を毎日30分以上(心血管病のない方が対象) |
| 5.節酒 | エタノールで男性20-30mL/日以下(日本酒1合程度) 女性10-20mL/日以下 |
| 6.禁煙 | - |
| 家庭血圧の装置 | 上肢カフ・オシオメトリック法に基づく装置 |
| 測定条件 | a;朝 起床後1時間以内、排尿後、朝の服薬前、朝食前、座位1~2分後 b;晩 就床前、座位1~2分後 |
(5)血圧の日内変動の評価と脳・心臓・腎臓・血管など高血圧による全身の臓器障害の有無を評価し、効率よく高血圧の治療方針を決定します。
“紹介状”をご持参ください
● 他の医療機関におかかりの方は、症状経過のわかる“紹介状”を必ずご持参ください。