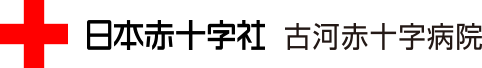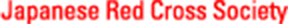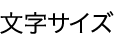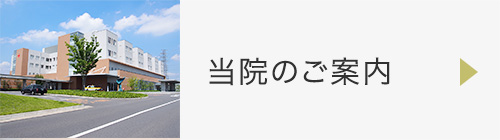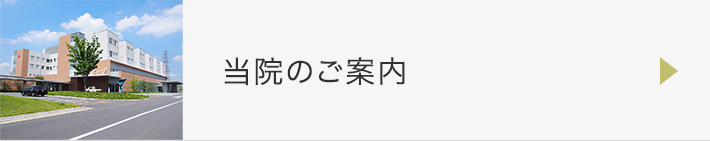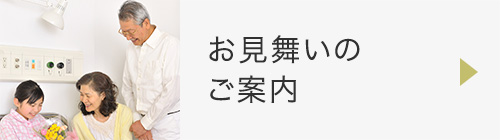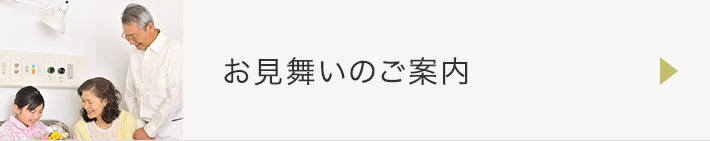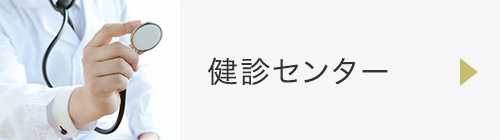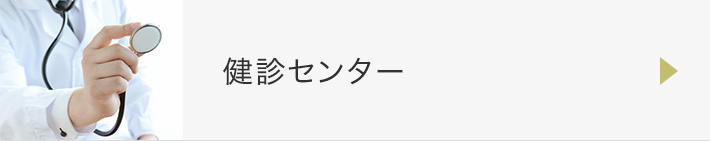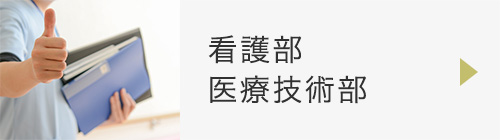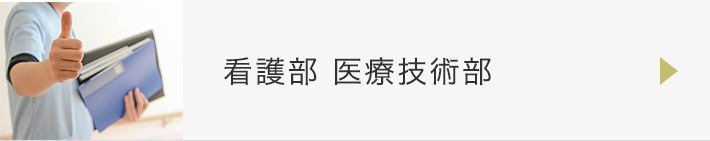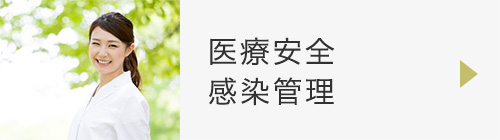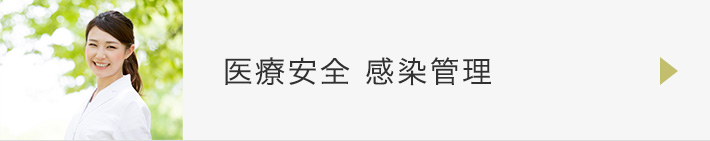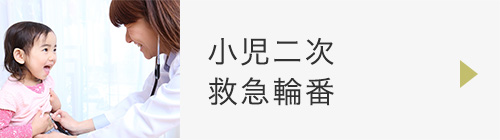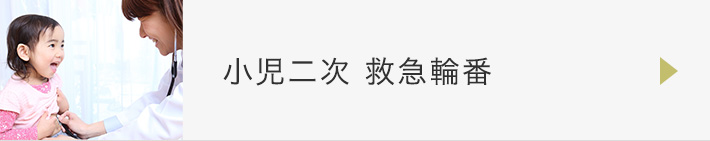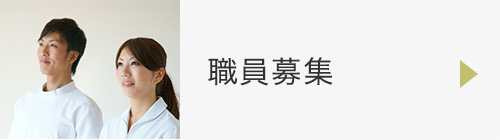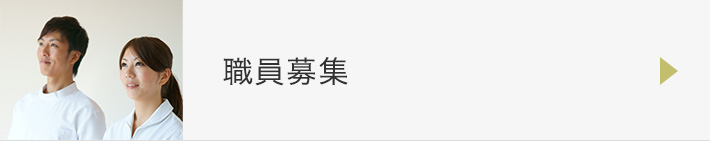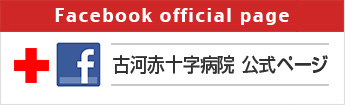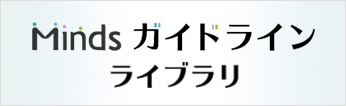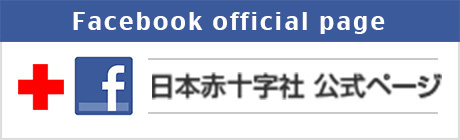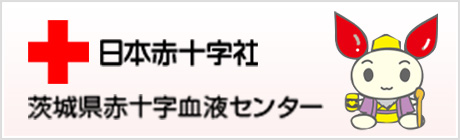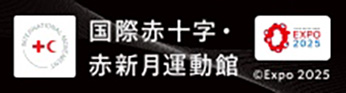職員募集
(公式)古河赤十字病院 HOME職員募集看護師(正職員・中途採用)
看護師(正職員・中途採用)
募集人数 |
若干名 |
| 応募資格 | 看護師免許取得者 |
| 就業時間 |
スケジュール勤務 |
| 給与 | ・日本赤十字社給与規定による(中途採用者は経験により換算あり) |
| 休日 | 《病棟》 |
有給休暇 |
年次有給休暇 1年につき24日(4/1〜翌年3/31)うち夏季休暇5日 |
福利厚生 |
健康保険、厚生年金、日赤企業年金基金、労働保険(雇用・労災)、全社的福利厚生制度、退職金制度、日赤グループ保険、財形貯蓄、日赤積立年金、育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休業制度 |
| 必要書類 | 自筆の履歴書(6か月以内撮影の写真貼付) |
応募締め切り |
随時(電話で事前にご連絡ください) |
選考日時および方法 |
随時(電話で事前にご相談ください) |
| 職場見学 | 随時(電話で事前にご連絡ください) |
| 応募・問合せ | 総務課 人事労務係 電話 0280-23-7111(代表) |